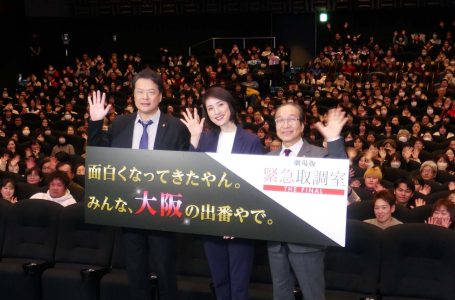『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』舞台挨拶 「ずっと大阪につながっていたんだ」
手塚眞監督が、手塚治虫原作で映画を撮る。それだけでニュースなのに、選んだ作品が『ばるぼら』である。1974年に発表されたこの漫画はエロスと狂気が錯綜し、さまざまなタブーも描かれた手塚治虫作品でも異色の問題作。ともすると悪趣味なエロティシズムに陥ってしまいそうな世界観を手塚監督は美しく映像化し、さらに稲垣吾郎、二階堂ふみという2人の俳優が原作漫画のキャラクターに生の厚みを加え、魅力的に体現している。
第32回東京国際映画祭(2019)をはじめ、世界各国の映画祭をめぐってついに日本での公開される本作について、手塚眞監督から詳しく語ってもらった。
つくりたい映画にぴったりの原作が、たまたま手塚治虫の漫画だった。
―― この映画は、どのようにして生まれたのですか?
5年くらい前に、大人向けのファンタジー映画をつくりたいと考えていました。ある程度エロティックで、思想的なものも含まれていて、外国映画のようなテイストをもった日本映画を撮ってみたいと。そんなときに子どものころから読んでいた『ばるぼら』を思い出して、読み返してみたら、ぼくがつくりたいと思っていたことがつまっていました。
「数ある手塚治虫の作品のなかから、なぜそれを選んだの?」と、よく質問されるのですが、漫画から選ぼうと思ったのではなく、“こんな映画をつくりたい”と思って素材を探していたら、たまたま父親のその漫画がぴったりだったということです。
―― 手塚治虫作品を映像化されるプレッシャーはなかったのですか?
ありませんでした。『鉄腕アトム』や『火の鳥』を映画にするのであれば、それなりに感じるかもしれませんが、『ばるぼら』はそんなに知られていませんから。でも、自分の好きな作品だし、自由につくれると思ったんです。
稲垣吾郎さんは「いつか、いっしょに仕事をしたい」と思っていた俳優。
―― 異常性欲に悩まされている小説家・美倉洋介という特異なキャラクターを演じるのが稲垣吾郎さん。キャスティングの意図は?
稲垣さんは以前から出演している作品を観ていて、「いつか、いっしょに仕事をしたい」と思っていました。そして、この映画の主人公・美倉洋介にぴったりだと気づいたのです。というのも、今回の映画には露骨な表現もあるため、品のある役者さんに演じてほしいと考えていました。その点で稲垣さんはステキなルックスをもっているし、品もある。さらに、インテリジェンスがありつつ、気取ったところや影も感じさせます。そのままの姿でいてもらえたら美倉になると思ったのですが、まさにハマりましたね。
―― この映画でも感じましたが、稲垣吾郎さんは彼にしかだせない不思議な雰囲気をもった魅力的な俳優ですよね。
稲垣さんはスターなのですが、スターらしくないのです。撮影現場でも誠実に接してくれましたし、自分が過激なキャラクターを演じることを理解したうえで、この役をとても楽しんでいました。
また、今回は意外性のある漫画を原作にしているので、いろいろな意味での“意外性”があればいいと思っていました。ぼくがこの原作を選ぶことに意外性があるし、稲垣吾郎さんが美倉を演じることもすごく意外性がある。それが、“ばるぼらの世界”だなと。
―― 対する二階堂ふみさんも、〈ばるぼら〉という存在をとても魅力的に演じています。
ぼくは、二階堂さんご自身をばるぼらっぽい人だと感じていたので、自由に演じてもらいました。二階堂さんご本人も「今までは役を演じるときに考えすぎていたから、今回は考えないでやりたい。衣装を身につけてカメラの前に立ったら感覚にまかせてやってみたい」といってくれたので、それでお願いしました。極端にいうと、ぼくは場所を指示するくらい。あとは二階堂さんにおまかせしたら、ばるぼらというキャラクターの不思議な厚み、たとえば人間くさいところとかも彼女が自然に表現してくれました。
―― 二階堂さんの肉体的な演技もすばらしいです。撮影は大変でしたか?
現場は和気あいあいとしていましたよ。もちろん緊張感はありましたが、必要以上に緊張せずリラックスして演じてもらえるよう、カメラマン以外は近寄らない状態にして撮影するなどしていました。
セクシャルな場面がたくさんある映画なので、二階堂さんには気になるところがあるのかを事前に確認したところ、彼女は「どこにもありません」と。また、かなり酷なシーンでは吹き替えを想定していたのですが、二階堂さんは「全部、自分でやりたい」といってくれました。それくらいの気持ちで演じてもらったので、とても演出しやすかったですね。
美しすぎるラブシーンを表現できるのも、映画ならでは。
―― 今回の映画は、ラブシーンがとても美しいと感じました。
ぼくはいつも、自分で映画をつくるときは“美しいものを撮りたい”と思っています。しかし、若いころに観ていた日本映画のラブシーンは、生々しいというか、汗臭いというか、美しさを感じるものがなかった。ですから、この映画ではラブシーンの美しさにはとくに気を使って撮ろうと思っていたのです。そして、カメラマンのクリストファー・ドイルや演者である稲垣さん・二階堂さんも、“(ラブシーンは)美しいほうがいい”という思いをもっていました。みんなが同じ思いをもって撮ったラブシーンは、美しくなりすぎたかもしれません。でも、それも映画ならではの表現だと思うのです。
―― 物語の舞台は、時代や場所を特定できない世界観で表現されています。
原作の漫画では新宿が舞台なので、その設定は変えずに新宿で撮影しています。でも、新宿という地域性のある映画にはしたくなったので、クリストファー・ドイルという海外のカメラマンの視点で切り取ってもらっています。
また、気づかれないと思いますが、効果音は世界中の音をミックスして使っています。雑踏の音や人の話し声、車の音など、実際の新宿の音に世界中の街の音を混ぜることで独特な世界観を感じてもらえるようにしました。
―― そのためなのか、新宿であって新宿でない、どこにでもありそうで、なさそうな街に感じました。
おとぎ話のような内容なので、特定の時代や場所にしてしまうとイメージが狭まってしまう気がしたのです。まずはイメージを解放して観てほしいと思って、映像も音もそういう作り方にしています。
―― 『ばるぼら』を撮影されたのはコロナ以前です。コロナ禍で世界が変わった今、改めてこの映画を観て、印象が変わったりしましたか?
とくにはありません。ぼくがこの映画をつくろうと思った問題意識のひとつに、世の中のデジタル化があります。リモートなどはコロナの前から進んでいて、ネットを通じてしかコミュニケーションを取れない、スマホでだけで完結するなど、相手と直接会わないで関係がつくられていくことに個人的には危惧があって。もっと人間同士でふれあい、カラダで確かめあって、感じてほしいと思っていました。だから、『ばるぼら』でのラブシーンは丁寧にしっかりと描いています。
世の中には、〈ばるぼら〉みたいなものがいる。それくらいの余裕をもって生きていきたい。
―― ところで、手塚監督は〈ばるぼら〉という存在をどう捉えているのですか?
映画のなかでは曖昧にしていますが、ぼくはもともと“街には妖精が住んでいる”という発想をもっていて、学生時代にはそのテーマで作品をつくっています。その土地にあるエネルギーみたいなものが具体的なキャラクターになるのもおもしろくて、今ならアマビエなんかも、一種の〈ばるぼら〉みたいな存在のように感じます。ぼくは、そういうものが世の中にいるという考え方は好きだし、そのくらいの心の余裕をもって生きていきたいと思っています。
―― 最後に映画『ばるぼら』を楽しみにしている人へのメッセージをお願いします。
この映画は、自分のなかにある夢の部分と理屈の部分の間にある葛藤みたいなところからできあがっています。映画に登場する主人公がそうですし、もしかしたら、原作者である手塚治虫自身もそうだったかもしれません。
これから観ていただく方には、全部を説明的に理解しようとするのではなく、イメージに対して心を開いて観てもらえると今までと違う映画体験ができるのではないかと思っています。ちょっと挑戦的な映画ですが、そこも含めて楽しんでもらえたらうれしいですね。
映画『ばるぼら』
2020年11月20日(金)より
なんばパークスシネマ、シネマート心斎橋、シネリーブル梅田にて公開。